屋根に太陽光パネルを設置した場合、雨漏りのリスクはないのか?
A.屋根材の種類によって、雨漏りのリスクを考慮すべき場合とそうでない場合があります。
要約
太陽光発電を載せた後、雨漏りは大丈夫なのか?:
雨漏りのリスクは屋根の種類と施工方法によります。 雨漏りのリスクは屋根の種類と施工方法で異なり、適切な対応で軽減可能です。ハゼ式折半屋根では屋根に穴を開けず、ハゼ部分に金具を固定するだけで設置できるため、雨漏りのリスクは極めて低いです。逆に、雨漏りの主因となる錆も、太陽光パネルの設置で直接の雨風が防がれるため、進行が抑えられるケースがあります。ただし、現状で雨漏りがある場合は、事前の改修が必要です。
ハゼ式の折半屋根と重ね式折半の対応方法:
ハゼ式は穴を開けず、重ね式はシール材で補強。 ハゼ式折半屋根は金具を直接ハゼ部分に固定するだけで施工でき、雨漏りリスクはほぼありません。重ね式折半屋根では、屋根に穴を開けてルーフボルトを差し込み、防水シール材で固定するため、多少のリスクはありますが、防水対策は十分に施されています。いずれも施工前の錆防止策や塗装オプションを選べる場合があります。
陸屋根の対応方法:
陸屋根は置き基礎と防水対策が鍵。 陸屋根では「置き基礎」を採用し、コンクリートブロックの重さでパネルを固定します。地域の風速や建物の高さを基にシミュレーションを行い、必要な重量を計算することで飛散リスクを防ぎます。また、防水シートを敷設するのが一般的で、定期的な張替えが求められます。既存の構造物とのバランスを考えた計算で、安全性を確保します。
解説者
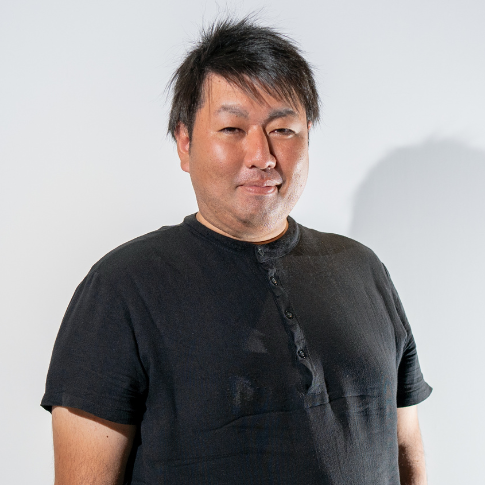
インタビュアー

太陽光発電設置における、雨漏り対策
━━━法人向け自家消費型太陽光発電設備の設置に際し、屋根に雨漏りのリスクがあるのではないかと心配されるお客様もいらっしゃると思います。そのような懸念に対して、どのようにご説明されていますか?
はい、ご心配される方は一定数いらっしいますが、実際には屋根材の種類によって雨漏りのリスクは異なります。
たとえば、よく採用されている「ハゼ式の折半屋根」についてご説明します。
このタイプの屋根では、パネル設置の際に屋根に直接穴を開けることはありません。金具をハゼと呼ばれる屋根の折り目部分に挟み込んで固定する方法をとるため、基本的に雨漏りのリスクは非常に低いです。
また、折半屋根は複数の金属板がかみ合うように組まれている構造になっており、ハゼ部分に金具を取り付けることで、逆に屋根の締まりが強くなり、全体の強度が高まるケースもあります。
もちろん、屋根材の種類によっては注意が必要な場合もあるため、恒電社では設置前に屋根の構造や状態を確認した上で、最適な設置方法をご提案するようにしています。
ちなみに、雨漏りの主な原因は「屋根材の劣化によるサビ」であるケースが多く見られます。
太陽光パネルを設置することで、屋根の一部が直接の雨や紫外線、風にさらされにくくなるため、サビの進行を抑える効果も期待できます。その意味では、太陽光パネルが屋根の保護となる側面もあるのです。
したがって、折半屋根の場合においては、太陽光パネルを設置したことで特別に雨漏りのリスクが高まるということは基本的にありません。
━━━となると、他の屋根のパターンはリスクがあるのでしょうか?
「重ね式折半」とも呼ばれるタイプですと、対応方法が異なります。この屋根では、「ルーフボルト」という部品を差し込み、固定します。
このタイプの場合、ハゼ部分のように掴める箇所がありません。そのため、どうするかというと、屋根に穴を開け、その部分にルーフボルトを差し込んで固定します。
屋根に穴が空きますが、ルーフボルトと屋根の間に、ゴムのシール材を使用します。このシール材を締め付けることで、屋根材に密着し、防水性を確保します。
━━━なるほど、それがハゼ式のくぼみの代わりになってくれるわけですね。
はい。先ほどご説明したハゼ式の折半屋根は、その構造上、屋根に穴を開けずに金具で固定できるため、施工によって雨漏りリスクが増えることは基本的にありません。
一方で、重ね式折半屋根の場合は、構造上どうしても屋根材に穴を開けて金具を取り付ける必要があります。そのため、ハゼ式に比べれば雨漏りリスクは若干上がるといえます。
ただし、重ね式折半専用の太陽光設置部材を使用しており、防水性能に配慮した設計になっていますので、しっかりとした対策は講じられています。
また、雨漏りのリスクに関しては「錆び」も大きな要因のひとつと説明しましたが、屋根の劣化が進み、錆びて穴が開いてしまえば、設置方法に関わらず雨漏りにつながる可能性があります。
恒電社では、施工前に屋根の状態を確認し、必要に応じて塗装などで強度を確保する選択肢もご案内しています。ただし、こうした補修や強化に関する投資判断は、お客様ご自身の設備方針に基づいてご検討いただいています。
参考記事
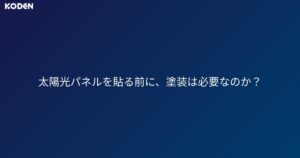
当社としては複数の選択肢をご提示し、その中から最も納得いただける形で進めていただけるようサポートしています。
━━━この2つ以外にも屋根のタイプがあるのでしょうか?
「陸屋根(りくやね)」と呼ばれるタイプの屋根があります。
これは、バルコニーや学校の屋上などでよく見られる、平らな構造の屋根です。おそらく、太陽光パネル設置において最も雨漏りのリスクが高いのが、この陸屋根タイプだと思われます。
というのも、陸屋根は基本的にコンクリートで形成されており、わずかなひび割れでも建物内部に雨水が侵入する恐れがあるためです。
このタイプの屋根には、「ウレタン防水」がもっとも一般的な防水方法として採用されています。液体状のウレタンを塗布し、防水膜を形成する方法で、仕上げとして防水シートを敷き、接着する場合もあります。ただし、この防水シートは数年に一度の張り替えが必要になるなど、定期的なメンテナンスが求められます。
よって、陸屋根に太陽光パネルを設置する場合、屋根にネジ(アンカー)を打ち込むような施工方法は、構造的・防水的な観点からほとんど採用されません。
一般的なのは「置き基礎」と呼ばれる方法です。
これは、コンクリートブロックなどを屋根の上に置いて重しとし、その上に架台とパネルを設置する方式で、屋根を傷つけずに施工ができるのが特徴です。
━━━もちろん十分な重さだと思うのですが、パネルを乗せるということは、強風が吹いた際に飛んでしまうリスクはあるのでしょうか?
はい、ご心配はもっともだと思います。ただし、その点もきちんと対策しています。
実際には、建物の高さや設置する地域の風の特性に応じて、重し(バラスト)の重さを調整しています。
たとえば、風が強い地域と比較的穏やかな地域では、当然必要なバラストの量も異なってきます。
具体的には、市区町村ごとに定められた基準風速と、建物の高さをもとに、屋根にかかる風圧を計算し、その数値に基づいて必要なバラストの重量を決めています。
また、弊社が使用しているシミュレーションシステムでは、こうした設置条件を入力することで、自動的に「このエリアには何kg以上のバラストを配置してください」といった具体的な指示が出る仕組みになっています。
ですので、設計段階で風によるリスクを十分に考慮した上で、最適な構成をご提案しています。
━━━素人的な質問ですが、重すぎると屋根にとって負担になるのではないかと思います。例えば地震が起こった際など、リスクはあるのでしょうか?
はい、ご指摘の通り、リスクが「ゼロ」というわけではありません。
ただし、それは太陽光パネルを載せること自体が問題というよりも、建物全体の構造の中で「どこにどれくらいの荷重がかかるのか」が重要になります。
たとえば陸屋根の場合、すでに空調の室外機やキュービクルなど、比較的大きな重量物が屋根の上に載っているケースもあります。それらと同様に、太陽光パネルや架台の重量を含めた上で、建物として安全に耐えられるかどうかを確認する必要があります。
※参考記事:太陽光発電設備の設置が、建物の耐用年数や保険料に影響を与えることはあるのか?
ただ、実際のところ、太陽光パネルの設置による平米あたりの荷重は約13kg前後とされており、特別重たいものではありません。
バラストは見た目にも「これで本当に飛ばないの?」と思われるほど軽く見えてしまうこともありますが、それでも風圧や地震を考慮した設計がされています。
また、強風が吹いた場合でも、下図のように風がパネルの上を通過することで、逆に屋根に押し付ける方向の力が働く構造になっており、飛散防止にもつながっています。
「風で飛ばないの?」と不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、例えばMRO JAPAN様が採用している置き基礎のシステムは実証済みです。
台風が多い沖縄の那覇空港で使用されており、2年間、2回の夏を越えても問題が起きていません。
参考記事:【導入事例】航空業界のMRO Japan株式会社が自家消費型太陽光発電を導入
━━━今回最後の質問になりますが、もし中小企業の経営者が自家消費型太陽光発電を導入する際に、雨漏りの観点で事前に自社の屋根で確認すべきことがあるとしたら、何をすべきでしょうか?
現在の時点で屋根に雨漏りがある場合は、太陽光パネルを設置する前に、事前に設備の改修を行っておくことをお勧めします。
ご不明な点があれば、まずは恒電社にお問い合わせくださいませ。
この記事を書いた人

