太陽光発電設備をスムーズに導入するために、発注前に準備すべきことは?
A. 電気使用量の明細や建物の図面、社内の調整体制などが揃っているとよりスムーズに進みます。準備が不十分でも当社がサポートいたしますので、ご安心ください。
事前に整理しておくとスムーズな情報
電気使用量の明細、建物や屋根の図面、予算・目的の明確化、社内の調整体制が揃っていると、検討から設計・申請、施工までの流れが効率的に進みます。ただし、建築図面がない場合も当社で対応可能で、全てが揃っていなくてもお気軽に相談できる体制を整えています。
納期遵守を支える柔軟な施工体制
天候や前工程の遅れが発生しても、後工程を先に進めたり、同時並行で施工するなど柔軟な対応で納期を維持することができる。必要に応じて作業工程を分割・再配置できる仕組みにより、実際に納期を守れなかった事例はこれまで一度もない。
解説者
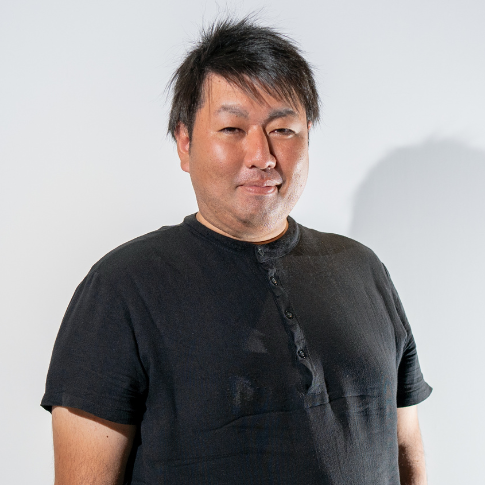
インタビュアー

スムーズな導入のために、発注までに準備しておくと良いこと
———ご検討から発注までの一連の流れをなるべく短くするために、お客様側で“発注前”に何か準備しておいた方が良いことはありますか?
まず前提として、私たちからお伝えしたいのは、「以下の要素がすべて揃っていなくても大丈夫です。お気軽にご相談ください」ということです。
実際、恒電社で手がけているプロジェクトの半分以上は、建築図面などの資料が完全には揃っていない状態からスタートしています。「準備が整っていないから相談しにくいかも…」と感じる必要はまったくございませんので、どうぞご安心ください。
その上で、強いて挙げるとすれば、以下のような情報をあらかじめ整理していただくことで、検討から設計・申請までのプロセスをよりスムーズに進めることが可能です。
- 電気使用量や契約状況の把握:過去1年分程度の電力使用量や電気料金の明細をご用意いただくと、施工会社(EPC事業者)が最適なシステム容量の設計する際に役立ちます。
- 建物や屋根の図面・資料:屋根や建物の構造に関する資料があると、初期検討や設計がスムーズです。
- 予算や導入目的の明確化:「どの程度の電力を自家消費したいか」「初期投資の目安はどれくらいか」など、導入目的が明確になっていると、より的確なご提案が可能です。
- 社内の調整体制:工事スケジュールや停電作業の調整などをスムーズに進めるために、お客様の社内での意思決定ルートを明確にしておくこともスピーディな導入につながります。
これらの情報が整っていれば、施工会社(EPC事業者)との打ち合わせがスムーズに進み、結果的に設置完了までの期間を短縮できます。
ただ、繰り返しになりますが、自家消費型太陽光発電の導入を検討し始めたお客様が「こういう準備が必要なんだ」とハードルを高く感じてしまう必要はございません。
例えば、建築図面についても、新築で自社が建てた建物なら確実に図面があると思いますが、中古で取得した建物の場合、図面がないケースもあります。そうなると「図面がないから諦めよう」となってしまうかもしれません。
そのような場合には、恒電社では、信頼できる調査会社や建築士のご紹介が可能であり、構造計算や荷重計算のについても間接的にサポートさせていただいております。
ただし、調査の実施有無や範囲の決定、それに伴う費用のご負担、さらに調査結果を踏まえた太陽光発電の導入可否の最終判断については、お客様ご自身の責任のもとご対応いただく必要がございます。
━━━導入目的については、事前準備が必須でしょうか
「高騰する電気料金の削減」や「CO2排出量の削減」といった大まかなニーズは、ある程度整理していただくと良いと思います。
一方で「いくら電気料金を削減したいか」「どの程度自家消費したいか」といった具体的な数値については、多くのお客様にとってイメージしにくいものだと思います。
よって、恒電社では現在ご利用されている電気量に応じたご提案を行っているため、事前に電気料金の明細をご用意して頂ければ、ご提案までの時間は短縮ができると思います。
スムーズに進まないケース
━━━過去には「施工がスムーズに進まなかった」という事例はありますか?
まず、これまで一度も納期を守れなかったことはないと自負しております。
というのは、太陽光発電の工事は、いくつかの大きな工程に分かれていて、一般的な建築工事とは異なり、各工程の順番を柔軟に入れ替えしやすいという特徴があります。
たとえば、ある工程に遅れが出たとしても、後続の別の工程を先に進めることでスケジュールを調整することができます。このように、工程をうまく組み替えることで、全体の納期に影響を与えにくい施工体制となっているのが特徴です。
━━━前の工程が遅れていても次の工程を進められるケースについて、何か具体的な例があれば教えていただけますか?
最も多いケースとしては「天候不良が続き、太陽光パネルの設置が完了しない場合」が挙げられます。
たとえば、パワーコンディショナの設置や、停電を伴う工事などは、パネル設置とは独立して進行できるため、工程の順序に厳密にとらわれる必要はありません。実際には、着工と同時に停電工事からスタートするといったケースもあります。
太陽光で発電された電気は、太陽光パネル → パワーコンディショナ → トランス → キュービクル
という流れで送られますが、この電気的なルートを構築する工事は、順番に縛られずに進めることができます。非活線状態(電気が流れないように)にしておけば、極端な話、すべて同時に施工することも可能です。
工程の順番前後する際に、より重要なポイントは「十分な人手が確保できるか」ということです。
━━━人手が十分に確保できると、なぜ工期が短縮できるのでしょうか?
通常、施工は四つのパートに分けて、一週間ずつ(計四週間)かけて順番に進めていきます。
もし十分な人員体制が整っていれば、これらのパートを同時進行で実施し、最短1週間で完了させることも“理論上”は可能です。
ただし、こうした短期集中型の進め方には注意点もあります。一つの作業でトラブルが発生すると、全体に影響が及ぶリスクが高くなるため、一般的には安全性と安定性を重視し、順番に進める方法を採用しています。
━━━一方で、スケジュールを前倒しとなり、予定より早くに工事が完了することはありますか?
四つのパートのうち、一つひとつの作業工程が短縮されることは十分にあります。
例えば、太陽光パネルの設置工程では、天候不良を想定してあらかじめ数日分の予備日をスケジュールに組み込んでいます。しかし、実際に天気が崩れなければ、その分作業を早めに完了させることができます。
ただし、一つひとつの作業工程が短縮が、全体のスケジュールに大きな影響を与えるかというと、そうとは限りません。
というのも、「停電工事の日程は事前に確定していること」がほとんどです。停電作業は、工場・設備の製造に直接的に影響を及ぼすため、あらかじめお客様の稼働スケジュール、ご担当者様のご都合、施工業者のリソースなどに合わせて慎重に日程調整しています。ですので、他の工程が前倒しで終わっても、停電日そのものを前倒しすることは現実的には難しいのです。
そのため、工事全体が予定より遅れてしまうことはもちろんありませんが、逆に大幅に早く終わるというケースも少なく、結果的に、スケジュール通りに着実に進行することがほとんどです。
この記事を書いた人

