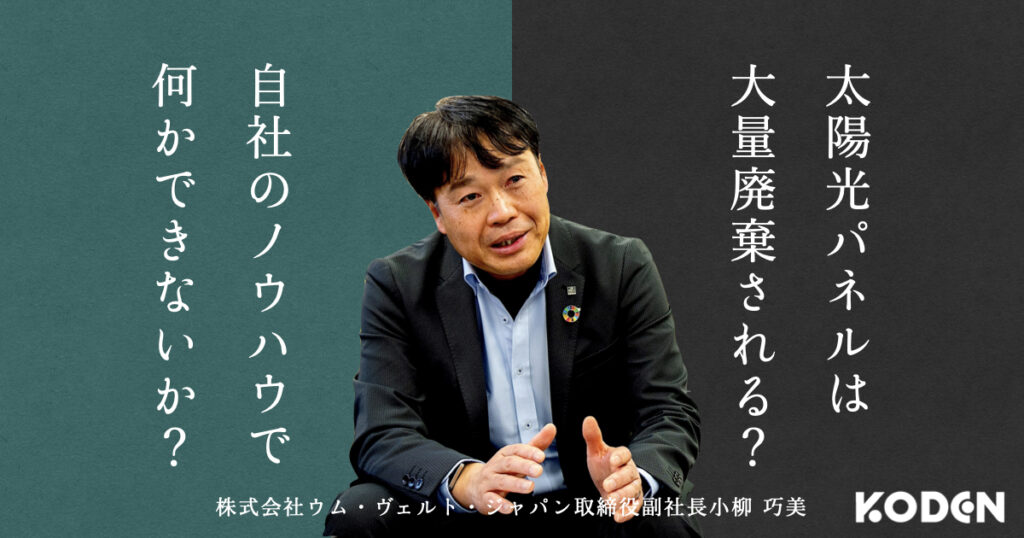【導入事例】地域の食文化を支える県北食肉センター様が自家消費型太陽光発電システムを導入|新しい世代の担い手を育成し、食肉産業をリードする基盤づくりへの挑戦

目次
【要約】地域の要として、食肉の安全・安心に供給
県北食肉センター協業組合について:県北食肉センター協業組合は食肉の流通合理化を目的に設立され、主に豚のと畜解体や食品カット加工を行う組合組織。組合員4社や関連業者が出資し、1日最大700頭の処理能力を備えている。利益を追求するよりも「食肉の安定供給」と「衛生管理の徹底」を重視し、地域の食文化を支える重要拠点として機能している。
自家消費型太陽光発電を導入した理由:電気代の高騰が続くなか、冷蔵・冷凍設備を常時稼働させる本施設では負担が深刻化。そこで堆肥化など他のコスト圧縮策と合わせて自家消費型太陽光発電システムの導入を検討する。適切なシミュレーションとリース活用で導入障壁を下げ、電気料金削減とCO₂排出の抑制を両立させている。
今後の展望:人材不足や高齢化への対応として、DX推進や自動化をさらに加速させ、先進的な食肉産業として地域から選ばれる施設を目指す同組合。埼玉県内のと畜場の集約化が見込まれる中でも、働きやすい環境の整備と業務効率化を同時に進めることで、新しい世代の担い手を育成し、食肉産業をリードする基盤づくりに挑戦していく。
食料品製造業|県北食肉センター協業組合
食肉卸売業者の合理化を目的として、2002年に誕生した県北食肉センター協業組合。コスト高騰が続く中でも「食肉の安定供給」と「衛生管理」を最優先に取り組み、食肉流通の合理化を図っています。
同組合は、食品価格への転嫁を抑えながらも持続可能な経営を実現するため、リースを活用した自家消費型太陽光発電を導入。冷凍・冷蔵設備が稼働する日中の電力をほぼまかなうことで、大幅な電気料金削減とCO₂排出の抑制を同時に達成しています。
『日々の自分の仕事が、地域の「食」を支えている。その誇りを胸に、スタッフが働いてくれるような環境づくりを進めていきたい』と語るのは、同組合の理事長・中村隼人様。今後はDXや自動化による作業効率化、埼玉県内と畜場の集約化への対応も見据え、さらなる進化を遂げようとしています。
今回はセンター長・荻野敦人様と共にインタビューにご協力いただき、太陽光発電システムの導入に至る背景や施工のプロセスなど、詳しくお話しを伺いました。
県北食肉センターの事業について

事業内容と設立の経緯
―――県北食肉センター協業組合様の事業内容について、教えていただけますでしょうか?
中村様:県北食肉センター協業組合は、食肉のと畜解体・加工業務を担う拠点です。食肉卸売業者の合理化を目的とした施設で、食肉流通の合理化を図っています。
組合員は、有限会社中村牧場、有限会社セーケン商事などの4社。また、組合以外にも数社が入っており、1日約700頭のと畜解体処理サービスと、併設の食品カットセンターの業務を運営しています。
組合員および利用者が協力する形でセンターを運営・活用しており、地域の畜産~食肉流通までの一貫体制を支えています。
―――協業組合設立の経緯について教えてください。
荻野様:2002年4月に、熊谷にあった埼玉県北部食肉センターと、川越を拠点にしていた食肉センターが統廃合し、現在の県北食肉センター協業組合が誕生しました。
その背景には、2001年に発生した牛海綿状脳症、いわゆる「BSE」を契機に高まった食品安全への関心があります。同年に「と畜場法」が改正され(施行は2002年)、高度な衛生管理と効率的な生産設備を整備する施設には補助金が交付されることとなりました。
こうした国や自治体の支援を活用し、全国各地で食肉センターの再編が進むなか、県北でも新たに協業組合としてスタートしたのが当センターです。

―――「高度な衛生管理と効率的な生産設備」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
中村様:例えば、トレーサビリティ(商品の生産から消費までの過程を追跡すること)の分野では、2004年以降にと畜された国産牛肉には個体識別番号の表示が義務付けられています。豚肉や鶏肉については法律での個体識別制度はありませんが、食肉事業者による任意の追跡システムや流通記録の管理が進んでいます。
また直近でも、2021年には「HACCP(ハサップ)」の義務化や食肉衛生検査の厳格化など、日本の食肉業界における安全基準は高まり続けています。こうした行政指針と衛生管理の強化を背景に、県北食肉センターは地域に欠かせない食肉流通のインフラとして機能しています。
HACCP(ハサップ):食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。引用:厚生労働省「HACCP(ハサップ)」

有限会社中村牧場との関わり
―――中村様は、県北食肉センターの理事長であると同時に、有限会社中村牧場様の代表取締役でもいらっしゃいます。食肉センター様と中村牧場様の関係について教えていただけますか?
中村様:県北食肉センターと中村牧場とは深い結びつきがあります。私の祖父である中村保一が農業から養豚場へ業種転換したのが1958年。その後、枝肉販売をメインとする問屋やカット肉の製造など、時代とともに業種を拡大・変革させてきました。1989年に、それまで市営だった食肉センター民営化に伴い、主要出資者として代表も務めるようになります。
現在も中村牧場は、当センターに多くの豚を委託と畜し、カットセンターも利用しています。規模としては全体のカット業務の7~8割以上が中村牧場によるものではないでしょうか。
荻野様:代表や責任者が重なる部分もあるため、外部から見れば同一に思われがちですが、民営化以前からの経緯もあって「県北センター = 中村牧場」ではありません。中村牧場は組合員として出資する“お客様”でもあり、互いにメリットを共有する組合員なのです。
―――ありがとうございます。そんな中村牧場様の視点、組合員としてのお立場から見た、県北食肉センターの存在意義や利点を教えてください。
中村様:県北食肉センターがあることで、生産からと畜・加工まで一気通貫の流通体制が整い、中村牧場を含む組合員にとって大きな経営メリットが生まれています。
個別のと畜場や市場を介して複雑な流通経路を辿ると、コストやリードタイムがかさみます。県北食肉センターという一括体制があることで、物流・衛生管理・品質保証などをまとめて最適化でき、組合員それぞれの負担が軽減されています。
また、生産者と流通・加工業者の目線が近い距離にあるため、消費者ニーズを捉えた製品開発や品質向上にもつなげやすい点も大きな利点です。
例えば、当社では「PORK LABO」というブランド兼直営店(EC含む)の運営もしています。自社で育てた豚を県北食肉センターに送り、そのまま解体・カット・包装などの加工まで行う。その過程での余計な輸送が減り、衛生管理の基準も組合全体で統一されているため、生産者としては「安全性を確保したままスピーディに市場へ届けられる」という安心感があります。

このように、県北食肉センターの存在は生産・加工・流通を一元化する拠点として、生産者と消費者を結ぶ架け橋になっています。単なると畜場としての役割を超え、組合員の利益や地域の食肉供給体制を支える要となっているのが大きな意義だといえます。
自家消費型太陽光発電システム導入のきっかけ・理由

自家消費型太陽光発電システム導入の背景
―――太陽光発電システムを導入しようと思った最大の理由を教えてください。
荻野様:電気料金の高騰を受け「長期的な施設運営コストを軽減したい」という思いが最も大きな動機でした。
2022年以降、燃料費調整額や再エネ賦課金が大幅に上昇し、電気代は想定以上の負担になっていました。特に夏場は冷凍・冷蔵設備がフル稼働するためピーク値が高くなります。一方、組合としては「農家や組合員に過度な負担をかけない」方針があるため、むやみに価格転嫁ができません。
中村様:もともと当センターは利益を追い求める施設ではなく、組合員や生産者の負担軽減が目的にあります。ゆえに「電気代が上がった分、料金にそのまま転嫁してしまえばいい」とはいきません。食品価格をなるべく安定させたいわけですからね。
自助努力で運営コストを抑えることを模索していた中、産廃費用を抑えるために、まずは堆肥化設備を導入して一定の効果を得ることができました。その成功体験から「次は電気代をどうにかしよう」と考え、自家消費型太陽光が候補として浮上しました。
金融機関からのご紹介も後押しにあり、さまざまなシミュレーションを重ねた結果、自家消費型太陽光発電が最適だという結論に至りました。繰り返しになりますが、こうしたコスト削減の取り組みは、最終的には「安定的な食肉供給」という組合の役割を守るために欠かせない手段となっています。

恒電社を選んだ理由
―――太陽光発電設備の導入にあたって、恒電社を選んでいただいた決め手は何だったのでしょうか?
中村様:各社から提案がある中で、恒電社のシミュレーションの分かりやすさと、屋根形状や日陰まで考慮した最適配置のプランが非常に納得できる内容でした。
一般的には「この屋根にこれだけ載せれば、これだけ発電して、これくらいの費用対効果です」と数値だけの説明が多いのですが、恒電社は金額やグラフ、イメージ図などを使って「休日の余剰はこれくらい出る」「どの時間帯にどれほど使える」と具体的な説明をしてくれました。
また、余剰電力が過度に発生しないように屋根の構造を細かく調査・検討していただいたり、日々の電気使用量や現在の電力契約と発電量シミュレーションを照らし合わせて見せてもらったことで、電気代削減のイメージも明確になりましたね。
屋根全体に目一杯載せるのではなく、当センターにとって最もメリットのある形でご提案いただけたのが信頼にも繋がりました。

荻野様:工事期間中の進捗報告の頻度もちょうど良かったです。1週間ごとに「今こういう段階です」「予定が少し変わりました」など細かい連絡をいただいたので、こちらも段取りが組みやすくトラブルもありませんでした。
技術的に分からない点も丁寧にかみ砕いて説明していただき、非常にスムーズに導入が進んだ印象です。
ご導入後の感想と満足度
―――実際に太陽光発電が稼働し始めてからのご感想はいかがでしょうか?
荻野様:シミュレーションどおり発電量が確保できており、休日を除けば、ほとんどが自家消費に回せていることに非常に満足しています。連休で稼働が少ない日は多少余剰が生じますが、それも想定内で、無理にパネルを載せすぎない設計が功を奏しています。
あとは、これから夏にかけてどう変化するかが楽しみですね。購入した電力を減らせるうえに、契約電力の上限を超えにくくなるのが大きいメリットだと考えています。これまでは冷凍・冷蔵設備が同時稼働するとピークを超過しやすく、追加料金が発生するリスクがありましたが、太陽光発電で日中の使用量を抑えられるようになると思います。
―――中村様はいかがでしょうか?
中村様:スマートフォンでもモニタリングできるので、1日に数回チェックしています。
天気が良い日は「しっかり発電してくれているな」とか、曇りや雨の日には「やっぱり発電していないな」と、落ち込みも可視化されて面白いですし、 発電量を常にリアルタイムで確認できるため、節電の意識醸成にも役立っていると感じますね。
無駄なく使える安心感と確かなコスト削減効果があり、導入して良かったと感じています。

―――逆に弊社のご対応の中で、課題や改善点があれば教えてください。
貴社に対しての課題ではありませんが、抱えている不安もあります。
当センターは、事業や地域の特性から屋根に鳥がとまりやすいので、糞や汚れがパネルに付着した場合は、定期的な清掃が必要になります。どのくらいの頻度がベストで、そのコストはどれほどか…これは稼働しながら実際に様子を見ていくしかありません。
また将来的に撤去をする際、産廃費用やリサイクル費用がどうなるのか。国や自治体で補助制度が整う可能性もありますが、現時点では見通しが立ちづらい部分ですね。
関連記事
今後の事業展望
―――県北食肉センター協業組合、および中村牧場としての今後の展望を教えてください。
中村様:日本の食肉産業は今後ますます集約化が進み、大規模化した施設が“選ばれる”傾向にあります。そんななかで人手不足や施設の効率化という課題を解決するため、DX推進やIT技術を本格導入し、さらに高度で衛生的な施設を目指していきます。
冷蔵・冷凍設備を回しながら空調もしっかり稼働させる。加えて新たな技術を導入するとなると、相当な電力がかかります。一方で、既にDXに成功している事例も海外には存在します。
たとえばオーストラリアなどでは、ロボットを活用してと畜や解体の一部を自動化し、高い効率と安全性を実現しています。県北食肉センターでも、動画マニュアルを作る試みを始めていますが、まだ試験導入の段階なので、組織体制やコスト面を含めてこれから本格化していきたいところです。
―――やはり食肉の領域でも、衛生、効率の両方において先進的な諸外国が存在しているのですね。
はい。もちろんその背景には、技術や先進性とは別に、食文化における根本的な“意識の差”も存在していると思います。
これまでアメリカやオーストラリアなどで多くの現場を見てきましたが、従業員さんの目の輝きが違うんですよ。「食肉」に対する認識が日本のそれとは異なる印象を受けました。
日々の自分の仕事が、地域の「食」を支えている。
その誇りを胸に、スタッフが働いてくれるような環境づくりを進めていきたいです。
———この度はインタビューにご協力いただき、誠にありがとうございました。

インタビュー・執筆・写真