【導入事例】食品製造業の株式会社フレッシュキッチン様が自家消費型太陽光発電を導入|365日稼働の食肉加工メーカーが目指す、安全・安心な食品づくりの現場

目次
【要約】電気代削減とCO2排出削減のため、埼玉県の省エネ診断を契機に太陽光発電を導入
株式会社フレッシュキッチンについて:2001年設立の株式会社フレッシュキッチンは、チルドの総菜半製品の製造を中心に事業を展開。鶏肉や豚肉を使用した未加熱加工品をスーパーマーケットや外食産業に供給している。特徴として、埼玉県と大阪府の2拠点体制で鮮度維持を重視した365日稼働体制を採用し、保存期間の短いチルド商品を安定的に提供している点が挙げられる。また、親会社であるフードリンク株式会社と協力しながら付加価値を創出する商品開発にも注力しており、調味料を投入するタイミングにこだわった二段仕込み・三段仕込みの味付け肉(店舗で唐揚げとして販売)や、販促シールや野菜など畜肉以外の食材を同じ出荷時に段ボール同封するキット商品等、顧客が調理しやすい製品を提供している。
自家消費型太陽光発電を導入した理由:事業の特徴から冷凍・冷蔵設備の電力消費が大きく、電気代高騰とCO2削減の必要性が経営課題であったことを背景に、埼玉県の省エネ診断を受診。診断結果と複数の改善案の中でも、投資とリターンのバランスが取れ、かつCO2削減に大きなインパクトがあった太陽光発電システムの導入の検討を開始した。埼玉センターでの過去の太陽光発電導入検討資料や他社提案と比較検討を行い恒電社を選定。親密なコミュニケーションを取りながら、機器の選定から工期スケジュールの調整など、丁寧な対応の結果、365日稼働を止めることなく導入を実現することができたとフレッシュキッチン関係者は語っている。現在、太陽光発電を通じてコスト削減と環境負荷軽減の両立を目指している。
今後の展望:太陽光発電を含めた取り組みを通じて、会社も社会の一員として、食品製造業として「安全・安心な食の製造を通じて社会に貢献する」ことに加えて、環境面でも持続可能な成長を実現するための努力を続ける姿勢を示している。導入後は日々の発電データの可視化を通じて、従業員の環境意識を高める取り組みも始めている。
食品製造業|株式会社フレッシュキッチン様
埼玉県と大阪府に拠点を構え、チルド食品の製造を中心に事業を展開する株式会社フレッシュキッチン様。365日稼働体制を整え、鶏肉や豚肉を使用した加工品をスーパーマーケットや外食産業に安定供給しています。
現場で働く従業員を大切にすることで、製造体制を支える強固な基盤を築いている同社は、電気代削減やCO2排出削減を目指し、省エネ診断を契機に2024年、自家消費型太陽光発電を導入されました。
自家消費型太陽光発電設備の導入に至った背景や、EPC業者を選定する上で考えたこと。
そして、今後企業としてどのような想いを持って経営していくのかなど、未来についてのお話もお伺いしました。
フレッシュな供給を支える365日の操業体制
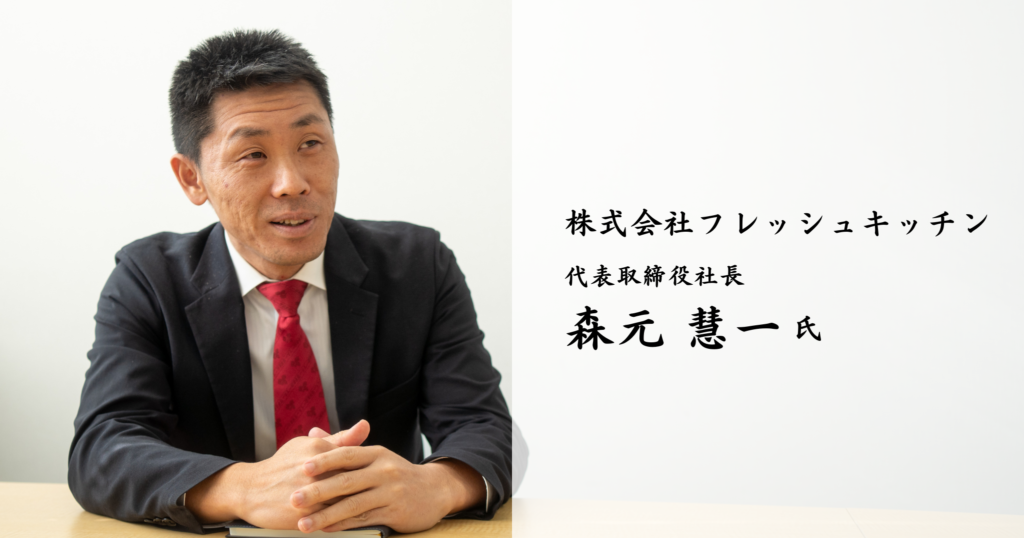
――― 御社の事業内容について教えていただけますでしょうか?
株式会社フレッシュキッチンは、2001年の設立以来、食肉加工を中心とした事業を展開してきました。主力製品は鶏肉と豚肉を使用した加工品で、特にチルド(冷蔵)状態での供給にこだわっています。
お客様は主にスーパーマーケット様や量販店様といった小売店様、そして外食産業の企業様が中心となります。
創業以来『安全・安心な食の製造を通じて社会に貢献する』という企業理念は変わっていません。ISO22000の認証も取得しており、品質管理には特に力を入れています。
――― 会社の人数構成についてお聞かせください。
埼玉センターではパートさん・派遣さん約150名・正社員約25名、大阪センターではパートさん・派遣さん約130名・正社員約15名が在籍しています。
――― 御社の特徴について教えていただけますでしょうか?
事業の特徴としては、埼玉と大阪の2拠点体制で365日稼働している点が挙げられます。
チルド商品は美味しく食べることができる賞味期限が短く、鮮度管理が極めて重要です。この体制があるからこそ、スーパーマーケット様や外食チェーン様に、新鮮で安全安心な商品を安定的に供給できています。
また商品開発の面では、当社の原料の仕入・商品開発及び製品販売を担う親会社であるフードリンク株式会社と一緒に特に力を入れているのが「付加価値の創出」です。
例えば、単純な切り身やスライスだけでなく、マリネ液に漬け込んだり、パン粉をつけたりして、お客様が調理しやすい状態まで加工しています。10年ほど前まではアウトパック(精肉加工)が中心だったのですが、現在はアウトパックはゼロとなりました。お客様のニーズの変化に合わせて、会社の強みを活かし内部を変化させ徐々に価値提供の幅を広げてきました。
「人」が強みの源泉

――― 御社の「強み」について、どのようにお考えでしょうか?
中道氏:繰り返しになりますが、大きな強みとしては「365日の年中無休での操業体制」があります。
チルド商品は徹底した温度管理が必要で、賞味期限が非常に短いのですが、365日フレッシュな状態でお客様にお届けできる体制を整えています。
冷凍ではなくチルド状態での供給を維持できているのは、現場を支える従業員の存在があってこそです。
私も現場でパート社員として働いていた経験がありますが、土日のシフトも含めて、正社員、パート社員、派遣社員の方々が連携を取りながら毎日出勤していただき、この体制を支えてくださっています。
――― これまで事業内容に変化はあったのでしょうか?
創業時はスーパーマーケット向けの精肉のカットとパック詰め(アウトパック事業)が主力でしたが、約10年前から大きく事業転換を行いました。外部環境の変化からアウトパック事業はお取引先様での内製化が進み縮小傾向となってきたのを期に、業務用商品の製造工場へと舵を切ったのです。
現在は味付け済みの商品など、より調理に近い商品の製造を行っています。例えば、スーパーマーケット様向けの唐揚げキット等は、味付け肉と唐揚げに使用する粉に加え、販売時に使用される販促シールを同封し、スーパー様現場側での負担を軽減するなど、付加価値の創出に取り組んでいます。
新しい取り組みには苦悩もありました。
まずアウトパック専用の機械を思い切って処分し、外食様向け製品の手作業での製造へと切り替えていく必要がありました。
その後、調味料を混ぜる機械や攪拌機など、新しい設備を順次導入。パン粉付けなど、それまでになかった工程にも対応できる体制を整えていきました。
新しいやり方に変えていくのは大変ではありましたが、全員で力を合わせて乗り越えることができました。

「働く人」の特徴
――― 貴社の社員の特徴について教えてください。
ほとんどの社員が食品業界の経験がない中で転職してきます。

―――小川さんのご入社のきっかけについて、お聞かせいただけますでしょうか?
小川氏:私の場合も少し変わっていて、食品業界で働きたいという明確な意思は正直なかったのですが、前職で食品に関係する仕事をしたことがあり、そこに通じるものがあるのかなと思い入社しました。
――― 入社してみて、想像と違った点について伺えますでしょうか?
良い意味で「工場勤務のイメージとの乖離」が大きかったですね。
工場勤務ではあまりコミュニケーションを取らずに、自分の担当部分だけをこなすようなライン作業のイメージを持っていたのですが、入社後は違いました。
特に埼玉センターでは、製造商品の頻繁な切り替えがある中で、社員同士、現場の方々がコミュニケーションを取らないと成り立たない関係性があります。そのため、他の工場よりも明るい職場という印象を持ちました。
――― 働いていてやりがいを感じる部分はどこでしょうか?
大規模な何百億円もする工場ではありませんから、工程を変更する際も、まずはやってみて、その正しさを確認しながら進めています。色々な人の意見を聞きながら試行錯誤を重ねています。
自分の中でも常に創意工夫をしながら、それをラインやオペレーションに落とし込んで変えていける。これは弊社ならではの特徴だと思います。
やろうと思った方にとっては、様々なチャレンジができる環境だと思います。
仕事をする中での充実感もそうですし、職場の雰囲気という部分については、社長含めてセンター長の皆様の意識的な工夫があるのではないかと思います。
――― 職場の雰囲気を意識的に明るくしたい、変えていきたいという背景があっての取り組みをされているのでしょうか?
中道氏:私が意識してきたのは、パートさんファーストという考え方です。これは今でも変わらない思いです。パートさんの気持ちを考えて動かないと、生産性は上がってきません。作業される方が気持ちよく働いていただけるような環境づくりを常に考えています。日頃のコミュニケーションはもちろん、待遇面でも配慮しています。
以前は不十分であったかもしれない福利厚生なども、現在は充実させています。例えばお肉のギフトセットを、パートさん、派遣さんも含めた全従業員に配布したり、暑気払いや忘年会・新年会も各現場毎に実施しています。本年度下期からは誕生日ギフトも始めました。

私たちの強みである365日体制は、現場で支えてくれる人がいなくなった瞬間に成り立たなくなってしまいます。
最も大切なポイントはやはり「人」なのです。
先ほど申し上げた切り替えが多い工程では、単純に機械に原材料を流すだけで完成するというラインは組めません。また、業績を上げていこうとすると、作業時間を短縮しながら生産量を増やすという、厳しい要求にも応えていかなければなりません。
このような状況で、もし現場が暗く、ストレスが溜まるような環境であれば、人は離れていってしまうでしょう。そのため、気持ちよく、明るく、楽しく働ける環境づくりが重要になってきます。
そういった背景からも、パートさんファーストという考え方が以前から根付いています。
――― 小川さんの視点から見て、会社の強みはどのようなところにあると思われますか?
企業としての「安定感」を強く感じています。
特にコロナ禍において、社会全体が不安定になり、多くの企業で仕事量が不安定になった中でも、弊社では現場の作業者の方々への影響を最小限に抑えようとする動きがあったように感じています。
新しく入ってこられる方々にとっても『ここは安定した職場です』と自信を持って言えます。
事実として、このコロナ禍でも生産量は比較的安定していました。
これはチルド食品を扱っているという特性と、消費者のお客様のポートフォリオがうまくバランスを取れていたためです。例えば、家庭で食事をされる機会が増えたことによりスーパーマーケット様向けの総菜製造需要は増加しました、また、外食メーカー様向けのテイクアウトの需要も増加しました。両方の市場に対応していたからこそ、全体としての仕事量を確保できたと思っています。
また、社長のご尽力も大きかったと思います。

――― 当時、社長はどのような判断をしたのでしょうか?
森元氏:コロナ禍で一部の基幹商品の生産が数ヶ月間ストップするという事態がありました。
特にパートさんは時給制で働いているため、仕事がなければ収入がゼロになってしまいます。またコロナが明けて将来的に需要が回復した時に、当社の強みを発揮するためには人材の維持が不可欠です。もしその時に、収入がゼロになってパートさんが転職してしまえば、その損失は取り返しがつきません。
そのような説明を親会社であるフードリンク株式会社にも納得して頂き、同社と連携して他品目の生産数量を上げるなどをして何とか乗り切れました。当社の従業員を守ることは、グループ全体にとっても重要だと理解していただき、支援していただきました。
現場を回っていると従業員の方々は疲労や困難を率直に伝えてくれます。これが理想的な状態だと考えています。仕事の見通しや情報共有を大切にし、フードリンク株式会社との密なコミュニケーションを通じて生産量の調整を行うのが日々の経営層の仕事だと考えています。

自分が食べたいと思うか?家族や友人に勧めたいと思うか?
――― 会社の歴史や変遷の中での工夫についてお話しいただきましたが、根付いている変わらない経営方針や、時代に合わせて変化させてきた部分について、教えてください。
製造ラインや工程は時代とともに変化してきましたが、「安全・安心な食品づくり」という価値観は一貫して受け継がれています。
これは事業継続に直結する重要事項です。取引先様や消費者の方からのクレームは即座に取引停止につながりかねないため、品質管理は最優先事項として位置づけています。
現場では、パートさんが機械や製品の異常に気付いた際、すぐに報告して対応できるように、今年度工務体制を強化しました。
日々の作業の中で培われる感覚と、問題を報告しやすい雰囲気づくりが、安全・安心な食品づくりの基盤となっています。
弊社が20年以上存続できているのも、この品質管理へのこだわりがあってこそです。
私たちは作り手であると同時に消費者でもあります。「自分が食べたいと思うか、家族や友人に勧めたいと思うか」という視点を大切にしています。
最近では、入り口上部に我々の出荷した商品がどのようにスーパー様の店頭で販売されているかが分かる写真を掲示する取り組みも始めました。実際の商品を視覚的に理解することで、単なる作業ではなく、誰かが食べる商品を作っているという意識が一層高まると良いと思っています。特に我々は自分たちが住んでいる地域のスーパーマーケット様に届ける商品も多いためです。
――― 小川さんは日々現場でどのような変化を感じていらっしゃいますか?
外国人従業員との協働における変化を強く感じています。
以前は日本語でコミュニケーションが可能な方が中心でしたが、現在では通訳を介する必要がある方も増えています。そういった方々を同じ基準で評価する方法を、現場レベルで模索しています。
この変化に対応するためにも、“カミナシ”という管理システムの導入やタブレットの活用など、DX化を進めています。また、口頭や紙ベースの作業説明を、動画を使って直感的に理解できるように変更するなど、常により良い方法を追求しています。
このような動きが、会社の競争力向上にもつながっていると感じています。
自家消費型太陽光発電を導入した理由
――― 太陽光発電を導入検討したきっかけについて教えていただけますでしょうか?
「省エネ診断士の方のご提案」がきっかけでした。
埼玉県の省エネ診断士による診断を受け、その際に将来を見据えた太陽光発電の導入を推奨されました。特に近年の電気代高騰も背景にあり、省エネ対策は重要な経営課題となっています。
太陽光発電については、以前から大手電力会社様などからも提案を受けていましたが、今回の省エネ診断を機に本格的な検討を開始しました。単なる電気代削減だけでなく、CO2削減という環境面での効果も、フードリンク株式会社を含むグループの方針と合致する点で重要でした。
当社は製造工場という性質上、特に冷凍・冷蔵設備による電力消費が大きな課題です。
年間を通じて一定の温度管理が必要なため、節電できる余地が限られています。LED照明への切り替えなどの省エネ対策は既に実施していますが、それでも電気代は経費の大きな割合を占めています。
「365日」・「冷凍・冷蔵管理が必須」という二重の要因で、電力消費は避けられません。これは当社の強みである製造体制を維持するために必要不可欠なコストです。そのような状況の中で、省エネ診断のアドバイスを受けた際に、太陽光発電の施工会社として「恒電社」さんがあることを教えていただきました。
――― 複数社あった中で、最終的に恒電社を選んで下さった理由を教えてください。
省エネ診断士の方のおすすめもありましたが、選定については慎重なプロセスを踏みました。
埼玉センターでの過去の太陽光発電導入検討資料や他社提案と比較検討を行い恒電社さんを選定しました。選定過程では当社の近くでの施工事例を実際に見学させて頂き、経営者様へ当初の計画と施工後の状態についてのインタビューまでさせて頂きました。その分、選定まで時間がかかってしまい申し訳ありませんでしたが…、辛抱強くご提案を続けて頂いて感謝しております。
恒電社さんの特に良いと感じた点は、質問に対する迅速で明確な回答と、毎回丁寧なご説明をいただけたことが印象的です。
――― 施工期間中の対応についてどのように感じられましたか?
施工期間中は、当社の製造スケジュールに合わせて作業を進めていただき、生産活動に支障をきたすことなく導入することができました。特に、強制的なスケジュールを迫られたという印象が全くなかったです。
当社のペースに合わせて柔軟に対応していただいた点、とても満足しております。
恒電社メンバーの声

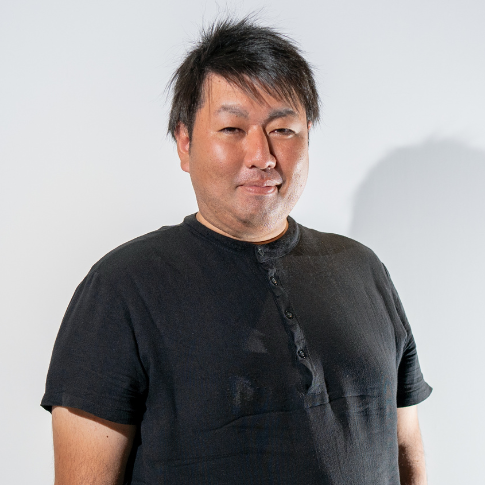
今後について
――― 今後、恒電社に期待することはありますか?
発電監視装置(ソフトウェア面での活用)については、より詳しい説明やご提案をいただけるとありがたいなと思います。
例えば、発電状況の確認や、データの活用方法などについて、より具体的なサポートがあれば、これからさらに効果的な運用ができるのではないかと考えています。
今後は、太陽光発電システムの導入効果を可視化し、社内で共有していくことも重要だと考えています。単なる設備としてではなく、会社の環境への取り組みの象徴として、従業員の環境意識向上にも活用していければと思います。
また、このような新しい取り組みを通じて、従業員全員が会社の成長や変革に参加しているという意識を持ってもらえることも期待しています。
――― 最後に今後の貴社の方針について教えてください。
最後になりますが、太陽光発電を含めた様々な取り組みを通じて、今後も従業員の皆さんに満足していただける職場づくりを続けていきたいと思います。
食品製造業として安全・安心な食品の提供はもちろんのこと、働く人々の幸せと会社の持続的な成長の両立を目指して、努力を重ねていきたいと考えています。

インタビュアー・この記事を書いた人

クリエイティブ担当

